【初心者向け】単元未満株(ミニ株)とは?1株から始める株式投資ガイド|メリット・デメリット、証券会社比較まで徹底解説
「株式投資を始めたいけど、何十万円も初期費用を用意するのは難しい…」「有名企業の株主になってみたいけど、株価が高くて手が出せない」
そんなふうに感じているビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。2024年から新NISA制度が始まり、個人の資産形成への関心は高まっていますが、株式投資の「まとまった資金が必要」というイメージは根強いハードルです。
しかし、その悩みを解決してくれるのが「単元未満株(たんげんみまんかぶ)」という仕組みです。この記事では、投資初心者の方でも安心して株式投資をスタートできるよう、単元未満株の基本からメリット・デメリット、おすすめの証券会社、さらには具体的な投資プランまで、わかりやすく徹底的に解説します。
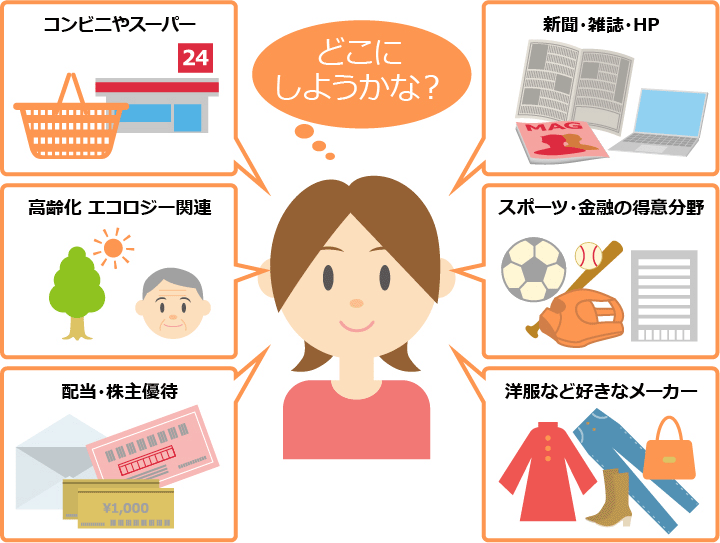
この記事を読めば、数千円という少額からでも憧れの企業の株主になる方法がわかり、資産形成への第一歩を具体的に踏み出せるようになります。
第1章:単元未満株(ミニ株)とは?〜1株から株が買える仕組み〜
まずは「単元未満株」がどのようなものなのか、基本から理解していきましょう。専門用語を避け、身近な例で解説します。
通常の株式取引(単元株)との違い
日本の株式市場では、通常、株は「単元(たんげん)」という単位で取引されます。多くの企業では1単元=100株と定められており、株を買うときは100株、200株、300株…というように、100株単位で購入するのが基本ルールです。
例えば、株価が5,000円の企業の株を買いたい場合、最低でも以下の資金が必要になります。
5,000円(株価) × 100株(1単元) = 500,000円
このように、まとまった資金が必要になるのが単元株取引のハードルでした。
一方、単元未満株は、この「100株セット」というルールに縛られず、1株から売買できるサービスです。先ほどの例なら、5,000円の資金があれば1株だけ購入できます。まさに、株式の「バラ売り」サービスと言えるでしょう。
この単元未満株は、証券会社が提供するサービスの名称で、会社ごとに以下のような愛称で呼ばれています。
- SBI証券:S株(エスかぶ)
- 楽天証券:かぶミニ®
- マネックス証券:ワン株
- auカブコム証券:プチ株®
基本的な仕組みは同じですが、取引ルールや手数料が少しずつ異なるため、後ほど詳しく比較します。
第2章:メリットだらけ!単元未満株を始めるべき5つの理由
単元未満株には、特に投資初心者にとって嬉しいメリットがたくさんあります。ここでは代表的な5つのメリットを解説します。
メリット1:数百円〜数千円の「超少額」で投資デビューできる
最大のメリットは、なんといっても少額から始められる手軽さです。 [1, 5] 例えば、誰でも知っているような有名企業の株も、1株単位なら驚くほど安く購入できます。
【1株ならいくらで買える?(例)】
※2025年4月4日の終値を参考にしています
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行):約1,500円
- KDDI(通信):約4,500円
- ソニーグループ(電機):約13,000円 [1]
このように、ランチ1回分や飲み会1回分程度の金額で、日本を代表する大企業の株主になることができます。 [10] これまで資金面で諦めていた方でも、気軽に投資の世界に足を踏み入れることが可能です。
メリット2:簡単に「分散投資」ができてリスクを抑えられる
投資の格言に「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉があります。これは、全ての資産を一つの投資先に集中させると、それが値下がりしたときに大きな損失を被ってしまうため、複数の投資先に分けてリスクを分散させましょう、という意味です。
単元未満株なら、この「分散投資」が非常に簡単に行えます。 [6] 例えば10万円の資金がある場合、単元株だと1社か2社の株しか買えないかもしれません。しかし、単元未満株なら10社や20社に分けて投資することも可能です。
- 金融株を3株
- 自動車株を2株
- IT関連株を5株
- 食品メーカー株を4株
このように、様々な業種の銘柄を少しずつ組み合わせることで、自分だけのオリジナル投資信託(ポートフォリオ)を作ることができます。 [6] ある業種の株価が下がっても、他の業種が好調であれば、全体の資産価値の目減りを抑える効果が期待できます。
メリット3:株数に応じて「配当金」がもらえる
企業が得た利益の一部を株主に還元することを「配当」と呼びます。単元未満株でも、保有している株数に応じて配当金を受け取ることができます。 [4, 8]
もちろん1株しかもっていなければ配当金も1株分(100株保有者の100分の1)ですが、銀行預金の金利と比べれば、はるかに高い利回り(投資額に対するリターンの割合)が期待できる銘柄も少なくありません。 [4]
配当金は、投資を続ける上でのモチベーションにもなります。年に1〜2回、企業の利益の分配金が自分の口座に振り込まれる体験は、投資の楽しさを実感させてくれるでしょう。
メリット4:新NISA口座の活用で利益が非課税になる
通常、株式投資で得た利益(値上がり益や配当金)には約20%の税金がかかります。 [9] しかし、NISA(少額投資非課税制度)という制度を利用すれば、一定の範囲内でその税金がゼロになります。
単元未満株もNISA口座で購入することができます。 [4, 8] 少額で得た利益や配当金から税金が引かれないのは、非常に大きなメリットです。
【重要ポイント】
NISA口座で配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定しておく必要があります。 [8] これは証券口座で手続きできるので、口座開設時に必ず確認しておきましょう。
メリット5:投資の「練習」に最適
いきなり大金を投じるのは誰でも怖いものです。単元未満株なら、まずは少額で実際の株取引を経験し、値動きの感覚や経済ニュースと株価の連動などを肌で感じることができます。 [10]
損失が出たとしても、投資額が少なければダメージも限定的です。 [11] この「お試し期間」を通じて、自分なりの投資スタイルを見つけたり、資金管理の重要性を学んだりすることができます。少額で経験を積んでから、徐々に投資額を増やしていくのが、失敗しにくい投資家になるための王道です。
第3章:始める前に知っておきたい!単元未満株の4つの注意点(デメリット)
多くのメリットがある一方で、単元未満株にはいくつかの注意点もあります。後で「知らなかった…」と後悔しないように、デメリットもしっかりと理解しておきましょう。
注意点1:取引時間や注文方法に制限がある
通常の株式取引は、証券取引所が開いている時間内(平日9:00〜11:30、12:30〜15:00)であれば、リアルタイムで好きな価格を指定して売買できます(指値注文)。
しかし、多くの単元未満株サービスでは、リアルタイムでの取引ができません。 [12, 13] 注文が出せるタイミングが1日に2〜3回(例えば、午前の取引開始時の価格や、午後の取引終了時の価格)と決まっています。 [5]
そのため、「この株価で買いたい!」と思っても、実際に約定(売買成立)するのは数時間後になり、想定と違う価格になってしまう可能性がある点は覚えておきましょう。 [12]
※ただし、後述する楽天証券の「かぶミニ®」など、一部リアルタイム取引に対応したサービスも登場しています。 [7]
注意点2:手数料が相対的に割高になることがある
1回あたりの取引金額が少ないため、手数料の割合が大きく感じられることがあります。 [13] 例えば、最低手数料が55円の場合、1,000円分の株を買うと手数料率は5.5%にもなります。
しかし、このデメリットは最近解消されつつあります。ネット証券を中心に手数料無料化の波が広がっており、SBI証券や楽天証券などでは、単元未満株の売買手数料が無料になっています。 [5, 6] 手数料を気にする方は、これらの証券会社を選ぶのが賢明です。
注意点3:すべての銘柄が買えるわけではない
単元未満株サービスでは、証券会社が対象とする銘柄しか取引できません。 [12] 東証に上場する全ての銘柄が対象ではないので注意が必要です。
とはいえ、日経平均株価を構成するような主要企業や人気の高い銘柄は、ほとんどの証券会社でカバーされています。自分が投資したい特定のマイナーな企業がある場合は、その証券会社で取り扱いがあるか事前に確認しましょう。 [12]
注意点4:株主としての権利が一部制限される
1単元(100株)を保有する正規の株主になると、株主総会に参加して経営に意見を言う「議決権」や、企業から商品やサービスがもらえる「株主優待」といった権利が得られます。
しかし、単元未満株の株主は、原則として議決権がありません。 [4] また、株主優待も「1単元以上の保有」を条件としている企業がほとんどのため、1株だけではもらえないケースが多いです。(一部、1株からでも優待がもらえる企業も存在します)
第4章:【徹底比較】初心者におすすめ!単元未満株が買える証券会社
では、実際に単元未満株を始めるには、どの証券会社を選べばよいのでしょうか。ここでは初心者におすすめの主要ネット証券を比較します。

| 証券会社/サービス名 | 買付手数料 | 売却手数料 | リアルタイム取引 | ポイント投資 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 (S株) | 無料 | 無料 | × (1日3回) | Tポイント / Ponta / Vポイント | 総合力が高く、手数料を完全無料にしたい人。ポイントの選択肢が欲しい人。 |
| 楽天証券 (かぶミニ®) | 無料 | 無料 ※リアルタイム取引はスプレッド0.22% |
○ | 楽天ポイント | 楽天ポイントを貯めている・使いたい人。値動きを見ながらリアルタイムで取引したい人。 [7] |
| マネックス証券 (ワン株) | 無料 | 0.55% (最低52円) | × | マネックスポイント | 買付手数料を抑えたい人。独自の分析ツールを使いたい人。 |
| PayPay証券 | 無料 | 無料 ※スプレッドあり |
○ | PayPayマネー/ポイント | PayPayユーザー。とにかく手軽に、100円や1,000円といった金額指定で始めたい超初心者。 [16, 17] |
※情報は2025年時点のものです。最新の情報や手数料の詳細は必ず各証券会社の公式サイトでご確認ください。
【結論】どの証券会社がいい?
- 手数料を最重視するなら:売買ともに完全無料のSBI証券が第一候補です。 [5]
- 楽天経済圏のユーザーなら:ポイントが使えてリアルタイム取引も可能な楽天証券が便利です。 [6, 7]
- スマホでゲーム感覚で始めたいなら:100円から金額指定で買えるPayPay証券が最もハードルが低いでしょう。 [16]
まずはこの3社の中から、ご自身のライフスタイルに合った証券会社を選んで口座開設してみるのがおすすめです。
第5章:【実践編】予算別!単元未満株で作るモデルポートフォリオ
「理屈はわかったけど、具体的にどう買えばいいの?」という方のために、予算別のポートフォリオ(金融商品の組み合わせ)例をご紹介します。ここでは、業種を分散させ、安定した配当収入(インカムゲイン)を狙うことを意識した組み合わせを考えてみました。

予算1万円コース:まずは投資を体験!
1万円でも、日本を代表する企業3社の株主になれます。様々な業種に分散するのがポイントです。
- 三菱UFJ (金融) 1株:約1,500円
- ENEOS (エネルギー) 1株:約800円
- KDDI (通信) 1株:約4,500円
合計投資額:約6,800円
生活に身近なインフラ企業を中心に組んでみました。残った予算で、気になる他の銘柄を1株買い足してみるのも良いでしょう。
予算3万円コース:分散先を増やして安定感をアップ
予算が3万円あれば、より多くの業種に分散できます。投資家・城晶子氏のポートフォリオを参考に、高配当株を組み込んでみましょう。 [11, 14]
- 三菱UFJ (金融) 2株:約3,000円
- ENEOS (エネルギー) 2株:約1,600円
- KDDI (通信) 2株:約9,000円
- JT (日本たばこ産業) 1株:約4,300円
- 東京個別指導学院 (教育) 1株:約500円
合計投資額:約18,400円
高配当で知られるJTなどを加えることで、受け取れる配当金の楽しみが増えます。 [11] このように1株ずつ買えば、合計2万円以下で多様なポートフォリオを組むことが可能です。 [15]
予算5万円〜10万円コース:高配当&成長性をバランスよく
このくらいの予算になると、安定的な高配当株だけでなく、将来の株価上昇が期待できる成長株(グロース株)も組み入れる余裕が出てきます。
- 【安定・高配当枠】
- 三菱UFJ (金融) 5株:約7,500円
- KDDI (通信) 3株:約13,500円
- JT (たばこ) 3株:約12,900円
- ENEOS (エネルギー) 5株:約4,000円
- 【成長期待枠】
- ソニーグループ (電機/エンタメ) 1株:約13,000円
- リクルートホールディングス (人材/IT) 1株:約7,000円
合計投資額:約57,900円
安定した配当収入を得ながら、一部の資金で将来の大きなリターンを狙う、バランスの取れたポートフォリオです。ご自身の興味のある業界や応援したい企業を選んで、オリジナルの組み合わせを考えるのがポートフォリオ作りの醍醐味です。
第6章:今日から始めよう!単元未満株 取引開始までの3ステップ
単元未満株を始めるのは、思ったよりも簡単です。口座開設はスマホで完結し、最短で翌営業日から取引が始められます。
- 証券会社の口座を開設する
まずは、第4章で比較した中から自分に合った証券会社を選び、公式サイトから口座開設を申し込みます。必要なのは、マイナンバーカード(または通知カード+運転免許証など)とスマホだけ。画面の指示に従って個人情報を入力し、本人確認書類をアップロードすれば、5〜10分ほどで申し込みは完了します。
- 口座に入金する
審査が終わると、IDとパスワードが通知され、取引ができるようになります。証券口座にログインし、投資に使う資金を入金しましょう。銀行振込や、提携銀行からの即時入金サービスが利用できます。
- 買いたい銘柄を選んで注文する
いよいよ株の注文です。証券会社のアプリやサイトで、買いたい企業名や銘柄コードを検索します。単元未満株(S株、かぶミニ®など)の取引画面を選び、買いたい株数を入力して注文を確定させます。指定された約定タイミングになると、自動的に売買が成立します。
まとめ:少額から始める「単元未満株」で、賢く資産形成の第一歩を
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- 単元未満株とは:通常100株単位の株を1株から売買できるサービス。
- 最大のメリット:数千円の少額から有名企業の株主になれ、分散投資でリスクを抑えやすい。
- 注意点:リアルタイム取引ができない場合が多く、議決権などの権利も制限される。
- 証券会社選び:手数料無料のSBI証券や、楽天ポイントが使えリアルタイム取引も可能な楽天証券が初心者におすすめ。
- 始め方:まずは1万円程度の予算で、複数の業種に分散して投資を体験してみるのが良い。
単元未満株は、これまで「お金持ちのもの」と思われがちだった株式投資のハードルを劇的に下げてくれる、画期的な仕組みです。少額で始められるからこそ、失敗を恐れずに実践的な経験を積むことができます。
この記事をきっかけに、ぜひあなたも「単元未満株」で資産形成の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。


