【初心者向け】自社株買いとは?株価が上がる仕組みや配当との違いを徹底解説
株式投資のニュースを見ていると、「〇〇社が自社株買いを発表」といったニュースを目にすることがあります。そして、その発表後に株価が大きく上昇することも少なくありません。投資家にとって「自社株買い」は、大きな利益のチャンスにもなりうる重要なイベントです。
しかし、「そもそも自社株買いって何?」「なぜ株価が上がるの?」「配当とはどう違うの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、そんな株式投資初心者の方に向けて、自社株買いの基本的な仕組みから、株価や会社の財務指標に与える影響、さらには配当との違いまで、専門用語をかみ砕きながら分かりやすく徹底解説します。
自社株買いとは?基本の仕組みと4つの目的
そもそも「自社株買い」って何?
自社株買いとは、その名の通り、企業が自ら発行した株式を、株式市場から買い戻すことを指します。自己株式の取得とも呼ばれます。 [1] 通常、私たちが株を買うのと同じように、企業が市場から自社の株を買い集めるのです。

企業が自社の株を買い戻すと、市場に出回っている株式の数が減ります。例えば、市場に100株が出回っていたところを企業が20株買い戻せば、市場の株は80株になります。すると、1株あたりの価値(希少価値)が相対的に高まることになります。 [1] この効果を利用して、企業はさまざまな目的を達成しようとします。
なぜ企業は自社株買いをするの?4つの主な目的
企業が自社株買いを行うのには、主に以下のような目的があります。
- 株主への利益還元
最も代表的な目的が、株主への利益還元です。市場の株数が減ることで1株あたりの価値が上がり、株価の上昇が期待できます。 [2] これにより、株主は保有している株の価値が上がるという形で利益を得ることができます。これは、現金を配る「配当」と並ぶ、重要な株主還元策の一つと位置づけられています。 [2] - 資本効率の改善と株価指標の向上
自社株買いは、企業の「成績表」ともいえる財務指標を良く見せる効果があります。特に重要なのが、EPS(1株当たり利益)やROE(自己資本利益率)といった指標です。 [1] 株数が減ることでEPSやROEは自動的に上昇し、企業の収益性や資本効率が改善したように見えます。 [1] これにより、投資家からの評価が高まり、株価上昇につながることがあります。 - 敵対的な買収への防衛策
株価が不当に安く放置されている企業は、他の企業から敵対的な買収を仕掛けられるリスクが高まります。自社株買いによって株価を引き上げたり、経営陣の持ち株比率を高めたりすることで、買収されにくくする防衛策として活用されることもあります。 [1, 2] - ストックオプションとしての活用
買い戻した株式は、役員や従業員へのインセンティブ(やる気を引き出す報酬)である「ストックオプション」に利用されることがあります。 [1] ストックオプションとは、自社の株をあらかじめ決められた価格で買うことができる権利のことで、従業員のモチベーション向上や、優秀な人材の確保につながります。 [1]
自社株買いが株価に与える影響
なぜ株価は上がりやすいのか?3つの理由
自社株買いが発表されると、株価が上昇しやすい傾向にあります。 [2] その背景には、主に3つの理由があります。
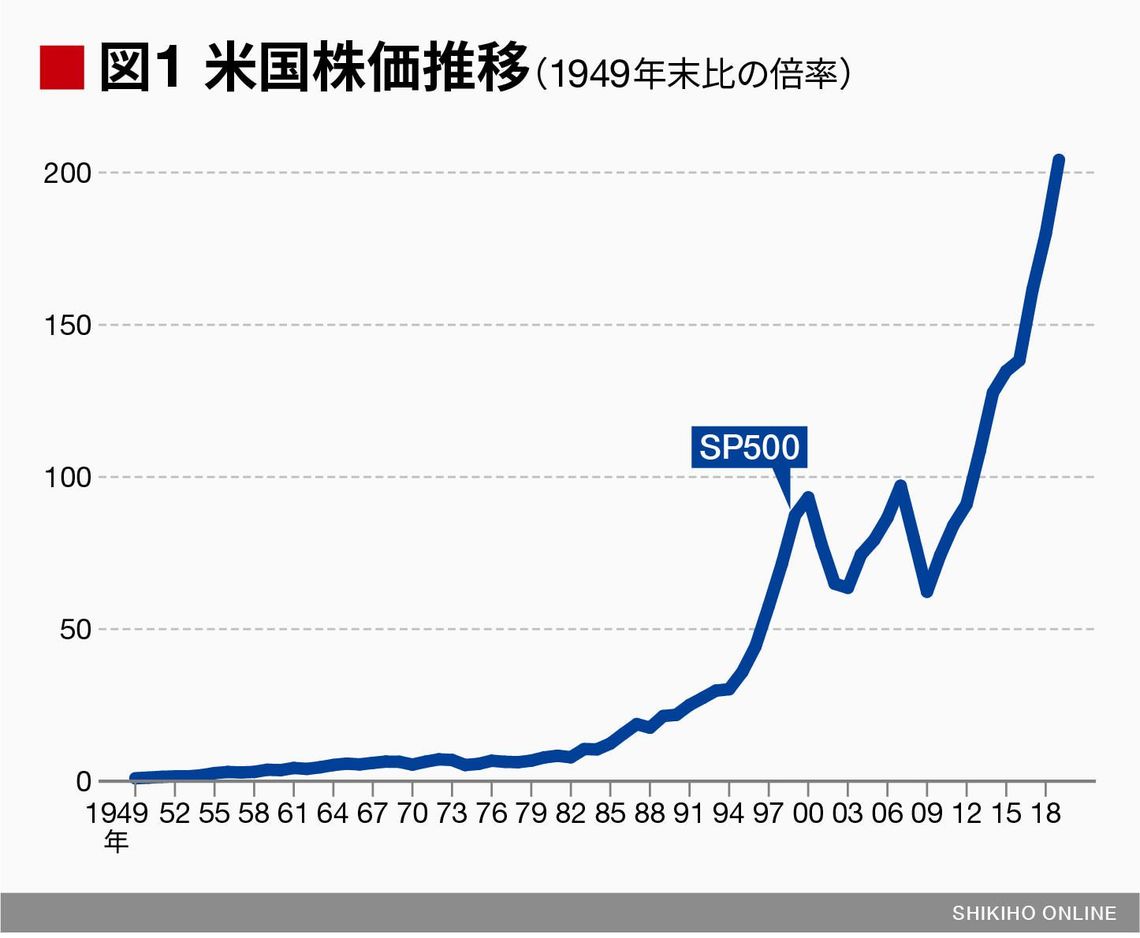
理由1:需要と供給の変化(需給の改善)
株式市場の価格は、買いたい人(需要)と売りたい人(供給)のバランスで決まります。自社株買いは、企業という大きな買い手が市場に参加することを意味します。買い注文が増える一方で、市場に出回る株の総数が減るため、「需要 > 供給」の状態になりやすく、株価が上昇する圧力となります。 [2]
理由2:1株あたりの価値(EPS)が上がるから
後ほど詳しく解説しますが、自社株買いをすると「EPS(1株当たり利益)」という指標が向上します。 [4] これは、会社の利益が変わらなくても、株数が減ることで1株が生み出す利益が増えることを意味します。1株の価値が高まるため、それが株価に反映されやすくなります。
理由3:経営陣からの「自信の表れ」というメッセージ
自社株買いは、「私たちの会社の株価は、本来の価値に比べて安すぎる」という経営陣からの強力なメッセージ(シグナリング効果)と受け取られます。 [2, 7] 会社の内部情報をよく知る経営陣が「今が買い時だ」と判断していることは、外部の投資家にとってポジティブな材料となり、買い安心感につながります。
注意!必ず株価が上がるとは限らない
自社株買いは株価にとってプラス材料ですが、万能薬ではありません。注意すべき点もあります。
- 上昇が一時的で終わるケース:発表直後に株価が急騰し、その後は利益を確定したい投資家の売りに押されて、元の水準に戻ってしまうことがあります(「材料出尽くし」)。 [2, 6]
- 市場の期待外れに終わるケース:発表された自社株買いの規模(金額や株数)が、投資家たちの期待よりも小さい場合、「がっかり売り」で株価が下落することもあります。 [6]
- 根本的な業績が伴わないケース:企業の業績そのものが悪化している場合、自社株買いの効果は限定的です。
- 財務の健全性への懸念:自社株買いは企業の現金(自己資本)を使って行われます。大規模な自社株買いは、企業の体力を削ぐことになり、財務の健全性を懸念した売りにつながる可能性もゼロではありません。 [2]
したがって、投資家としては自社株買いのニュースだけで飛びつくのではなく、その企業の業績や財務状況、市場全体の地合いなどを総合的に見て判断することが重要です。 [1]
重要な株価指標(EPS・ROE・PER)はどう変わる?
自社株買いを理解する上で欠かせないのが、企業の価値を測る「株価指標」への影響です。特に重要な3つの指標、EPS・ROE・PERがどのように変化するのかを見ていきましょう。

EPS(1株当たり利益)の上昇 → 1株の稼ぐ力UP!
EPS(Earnings Per Share)は、会社が1年間で稼いだ利益が、発行済み株式1株あたりいくらになるかを示す指標です。 [4] 計算式は以下の通りです。
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済株式数自社株買いをすると、この計算式の分母である「発行済株式数」が減少します。そのため、たとえ会社の利益(分子)が変わらなくても、EPSの値は機械的に上昇します。 [4]
【具体例】
純利益100億円、発行済株式数1億株の会社の場合…
EPS = 100億円 ÷ 1億株 = 100円
この会社が2,000万株の自社株買いを実施し、発行済株式数が8,000万株に減ったとすると…
EPS = 100億円 ÷ 8,000万株 = 125円
このように、会社の利益は同じでも、1株あたりの利益が100円から125円にアップしました。 [4] これが「1株の価値が高まる」ことの正体であり、株価を押し上げる要因となります。
ROE(自己資本利益率)の改善 → 資本効率UP!
ROE(Return On Equity)は、株主が出したお金(自己資本)を使って、企業がどれだけ効率的に利益を上げているかを示す指標です。 [1] 計算式は以下の通りです。
ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100 (%)自社株買いは、会社の現金(自己資本の一部)を使って行われます。そのため、分母の「自己資本」が減少します。結果として、利益が同じでもROEは改善します。 [1] ROEが高いほど「少ない元手で上手に稼いでいる会社」と評価され、投資家からの人気が高まります。
PER(株価収益率)の低下 → 割安感UP!
PER(Price Earnings Ratio)は、現在の株価が会社の利益(EPS)の何倍まで買われているかを示す指標で、株価の割安・割高を判断するためによく使われます。計算式は以下の通りです。
PER = 株価 ÷ EPS自社株買いによってEPSが上昇すると、この計算式の分母が大きくなります。そのため、株価が変わらなければ、PERは低下します。 [1] PERが低いほど、その株は利益に比べて「割安」と判断されやすく、新たな買いを呼び込む要因となります。 [1]
「自社株買い」と「配当」はどう違う?
自社株買いと配当は、どちらも代表的な株主還元策ですが、その性質は大きく異なります。 [2] どちらが良いというわけではなく、企業はそれぞれのメリット・デメリットを考慮して使い分けています。その違いを表で比較してみましょう。
| 項目 | 自社株買い | 配当 |
|---|---|---|
| 還元方法 | 株価上昇による間接的な還元 | 現金の直接的な支払い |
| 株主の受取 | 株を売却して初めて利益が確定 | 保有しているだけで現金がもらえる |
| 株価への影響 | 上昇要因になりやすい [2] | 権利落ちで一時的な下落要因になる [2] |
| 企業の柔軟性 | 業績に応じて機動的に実施・中止しやすい [2] | 一度増やすと減らしにくい(減配は悪材料) [2] |
| 税金 | 株を売却するまで課税されない | 受け取るたびに課税される |
最近では、企業は配当だけ、自社株買いだけでなく、この2つを組み合わせた「総還元性向」(利益のうち、配当と自社株買いの合計でどれだけ株主に還元したかを示す割合)を重視する傾向が強まっています。 [9] 安定的な還元は「配当」で、一時的な利益や余剰資金の還元は「自社株買い」で、というように使い分けることで、より柔軟な株主還元を目指しているのです。
ケーススタディ:有名企業はこう活用している!
実際に、日本の有名企業がどのように自社株買いを活用しているのか、いくつかの事例を見てみましょう。
- トヨタ自動車(7203)
日本を代表する企業であるトヨタは、継続的に大規模な自社株買いを実施しています。数千億円から1兆円を超える規模の自社株買いを何度も発表しており、安定的な増配と組み合わせることで、株主価値の向上を明確に打ち出しています。 [10] - ソフトバンクグループ(9984)
株価のテコ入れ策として、非常に大胆な自社株買いを行うことで知られています。2018年や2020年には、株価が低迷したタイミングで数兆円規模の巨額な自社株買いを発表し、株価を急騰させました。 [10, 11] 経営者の強い意思を示す好例です。 - 任天堂(7974)
2019年、大株主だった銀行が保有株を売却するのに合わせて、市場への影響を和らげるために自社株買いと自己株の消却(買い取った株をなくしてしまうこと)を発表しました。 [7] このように、特殊な需給要因に対応するために活用されるケースもあります。 - ファーストリテイリング(9983)
ユニクロを展開する同社は、対照的に自社株買いをほとんど行ってこなかった企業として知られます。 [12] 利益を株主還元よりも事業の成長投資に優先的に振り向けるという経営方針の表れと言えます。ただし、近年の市場の要請から、今後の動向が注目されています。 [13, 14]
このように、自社株買いへのスタンスは企業戦略によって様々です。その企業のIR(投資家向け情報)資料などを確認すると、なぜ自社株買いを行うのか(あるいは行わないのか)という考え方を知ることができます。
まとめ:投資家は自社株買いをどう見ればいい?
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 自社株買いは、企業が市場から自社の株を買い戻すことで、1株あたりの価値を高める株主還元策。
- 「需給改善」「EPS向上」「経営陣の自信の表れ」といった理由から、発表されると株価が上昇しやすい。
- ただし、株価上昇は一時的だったり、業績が伴わなかったりするケースもあるため、ニュースだけで飛びつくのは禁物。
- 配当とは性質が異なり、企業は両者を柔軟に使い分けている。
- 投資する際は、自社株買いのニュースだけでなく、その企業の業績や成長戦略も合わせて総合的に判断することが何よりも重要。
自社株買いは、企業の財務戦略や株主への姿勢が表れる興味深いアクションです。「なぜこの会社は今、自社株買いをするのだろう?」と一歩踏み込んで考えてみることで、より深く企業を分析する力がつき、投資の成功確率を高めることができるでしょう。


